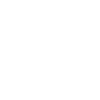一、御屋形 勝成公御一代本丸に被成御座、勝俊公御代ニ丸に御屋形を御建御移、夫より松平忠雅公、当 御代迄、二代(丸か)に被成御座候。忠雅公御参勤之節ハ、御本丸ゟ御発駕被成、御帰城之節も先御本丸へ御入、それよりニ丸之御屋形へ御移被成候由。
虎之間 御玄関なり、敷台の上に牡丹ニ獅子の彫物有、尤極彩色なり、九間半拾間半。
内玄関 四間ニ五間 御玄関より書院へ取付の溜を仙人の間と云。
書院 八間、拾壱間 皇帝の間と云。
御殿 八間、八間半 箱棟に葵の御紋付、御殿の内惣張付墨絵の山水、合天井秋野の七種、いつれも狩野永徳筆なり。是は伏見より御拝領なり。
御居間 六間、拾弐間 大津之景を描。
右之御間惣張、障子の腰、杉戸、唐紙、不残極彩色なり。
料理間 五間、拾弐間
御台所 七間、拾弐間 勝成公、相撲を好せられ、此所の庭にて御覧被成候由。高サ壱間壱間半四方ほどの高欄付たる箋(棧か)敷有。
奥御居間七間拾壱間 同御台所四間八間 御居長局 享保十五戌年崩、江戸へ被遣。
下台所六間九間戌年ゟ以前に被崩。
御風呂屋 伏見ゟ御拝領、鉄門番所之上に有。
一、鐘撞堂 鐘差渡弐尺五寸高サ四尺五寸龍頭マテ 太鼓差渡三尺長サ三尺五寸
一、櫓
三階櫓 伏見ゟ御拝領、筋鉄門之前に有、城付武具入。
火灯櫓 右同断 時之鐘之後に有。
月見櫓 右同断 東方御殿之後に有。
右いつれも戸柱などに松の丸と書付有。
櫛形櫓 神辺ゟ来 柏木番所之前に有。弓鉄砲其外武具入
神辺一番櫓 右同断 右番所之後、西南之角に有、寺社方帳面入。
同二番 同三番 同四番 右何れも西之方ニ有。
人質櫓 神辺ゟ来 乾之方に有。
荒布櫓 右同断 坤之方に有。
鹿角菜櫓 右同断 東坂口門之上に有。
玉櫓 右同断 天守之後、東之角に有。
塩櫓 右同断 天守之後、西之角に有。
亭櫓 東之方ニ有。
天守付櫓
右之外渡り櫓有。絵図にて可考。(絵図は本書にない)
一、門
鉄門 此門之上、武具入 東方武者走へ出小門升形之内ニ有
西坂口門 埋門有、西方武者走ヘ出ル忍口なり。
筋鉄門 東方帯曲輪ヘ出、小門有。
棗門
馬出門 チヤノコ門とも云。
蔵口門
東坂口門
下台門
台所門
一、清水
西坂口門之内壱ヶ所
東坂口門之内壱ヶ所
地蔵之清水 此清水之外側に六地蔵有常興寺繁栄之節よりの地蔵也。
一、井
鉄門升形之内ニ壱ヶ所
御台所脇ニ壱ヶ所
一、番所
筋鉄門之内壱ヶ所
坂上
鉄門
馬出門之外、藪之内壱ヶ所有之、御長抦之者壱人ッ、番相勤候所、近年相止。
一、渡櫓三百八拾間、多門一軒分伏見より御拝領。
一、天守之後帯曲輪、蔵口門之外、御城米蔵有、五千石と云。
水野家の御代より壱万石御預米有五千石を浜の蔵に入、五千石ハ此蔵に被入置、依而五千石共御城米共云。然處近来御用米と可唱由被仰渡、正福公御代対州府中へ弐千百石長州赤間か関江七千二百石、御廻米被仰付、其以後御預米無之故、廻場役所等も朽倒れ、御蔵も大破に及候に付、三間拾間の蔵弐ヶ所、三間ニ弐拾五間之蔵壱ヶ所、寛延三年之春被崩。三間ニ拾間之蔵三ヶ所、三間弐拾五間の蔵一ヶ所相残。